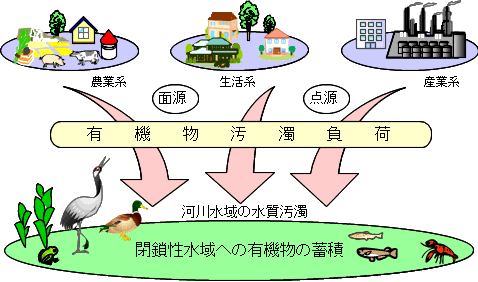§3.水質問題

日本の水危機では、特に水質問題が主要な問題とされています。河川や湖沼などの水環境が水質汚濁する現象は、流域内の人口増加、都市化に伴う人口集中、及び産業の急激な拡大など豊かな生活から排出される汚濁負荷量が増加し、それらに対する流域内での対応が遅れ、流出する汚濁負荷量が水域のもつ自浄能力を超えるところから進行します。最終的に河川が放流される海域においても連鎖的に水質汚濁問題が発生します。
それら水質汚濁問題は、生活や産業に重大な悪影響を与え、生態系への影響も大きく、水生生物の生きる場所を奪い生物多様性をも阻害し、水産資源の減少へも繋がります。
水環境問題の原因と現状
水質問題は、人間の健康や生活環境、水生生物に大きな影響を与えることから、日本では環境基本法に基づいた環境基準として水質の基準が定められています。昭和46年の環境基準の告示以来、河川ではBOD(Biochemical Oxygen Demand;生物化学的酸素要求量)の環境基準達成率が大幅に改善され、平成19年には90%に上昇していますが、湖沼のCOD(Chemical Oxygen Demand;化学的酸素要求量)の環境基準達成率はきわめて低く、ここ数年である程度改善されたものの、いまだ50%程度の水準に過ぎません。
湖沼、内湾、内海などの閉鎖性水域での富栄養化が進み、環境基準の達成状況をみても、河川や海域等に比べて依然として達成率が低く、特に湖沼の水質改善が急務となっています。
発生源別に汚濁負荷量を見ると、特定汚染源(点源)負荷量は減少傾向にあるものの、非特定汚染源(面源)負荷量の削減は進んでおらず、全体の負荷量に対する面源負荷量の占める割合は増加傾向にあります。
水質環境基準は「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」の2種類の項目が環境省により定められており、前者の健康項目にはカドミウムなど26種類の化学物質が対象とされ、後者の生活環境項目は、河川、湖沼、海域ごとに基準値が定められています。
環境省「水質汚濁に係る環境基準について」
水質環境基準(生活環境項目)の内容
| 項 目 |
内 容 |
| pH |
水素イオン濃度指数。水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す。 |
| BOD |
水中の微生物が呼吸や分解作用の時に消費する酸素量のことで、河川での有機物質による汚濁を測る代表的な指標のひとつ。 |
| COD |
水中の有機物を加熱分解する時に消費される酸化剤の量を、酸素量に換算したもの。主として、有機物による水質汚濁の指標として用いられており、湖沼及び海域で環境基準が適用される。 |
| SS |
Suspended Solid(浮遊物質量)の略称。懸濁物質ともいう。水の濁り度合いを表し水中に浮遊、分散している粒の大きさが2mm以下1μm以上の物質を指す。
|
| DO |
Dissolved Oxygen(溶存酸素量)水中に溶けている酸素量のことで、主として、有機物による水質汚濁の指標として用いられている。 |
| 大腸菌群数 |
大腸菌または大腸菌と性質が似ている細菌の数。主として、人または動物の排泄物による汚染の指標として用いられている。 |
全窒素
(T-N) |
窒素を含む化合物の総称。大量に流入すると富栄養化が進み、植物プランクトンの異常増殖を引き起こすとみられている。 |
全リン
(T-P) |
リンを含む化合物の総称。大量に流入すると富栄養化が進み、植物プランクトンの異常増殖を引き起こすとみられている。 |
| 全亜鉛 |
亜鉛を含む化合物の総称。大量流入すると水生動物に影響を与えるとみられる。 |
汚濁した河川、湖沼の水質問題は、悪臭の発生、水生生物の生育環境の悪化、さらに無生物化等生態系への悪影響、工業、農業、生活水利用も不適合となるなど、生活や産業経済活動への支障と環境破壊などをもたらします。さらに、水質問題には流水状態で起きる現象とは別に停滞水域でも固有の現象から生じる問題があります。
ダム湖や湖沼、河川内の堰上流滞水域などでは、流速が停止し滞留することで浮遊粒子などが沈殿除去される浄化機能がありますが、上流に汚濁源となる点源負荷がある場合や流域の面原負荷により窒素やリンを含む水が停滞水域へ供給されると、太陽光や増殖時間が確保され、植物プランクトンの発生など富栄養化現象という水質問題が現れます。
湖沼等の水質に影響を与える原因にはさまざまなものがありますが、大きく分類すると、流域から流れ込む「外部負荷」、湖沼内の生物などによる「内部負荷」、及び降雨などによる「直接負荷」に分けることができます。
湖沼水質に影響を与える負荷の例
| 区 分 |
影響を与える負荷の例 |
| 外部負荷 |
点源負荷 |
・生活排水
・工場、事業場排水
・畜産排水 |
| 面源負荷 |
・市街地
・農地
・森林 |
| 内部負荷 |
・底泥からの溶出
・湖沼での生物生産 |
| 直接負荷 |
・降雨
・養殖 等 |
※ 外部負荷 :流入河川および残流域から湖沼等へ流入する負荷
内部負荷 :底泥からの溶出、湖内での生物生産等の負荷
直接負荷 :湖面に直接降る雨および湖内での養殖等による負荷。湖沼等に直接湧出する地下水
による負荷も含む
点源負荷 :汚濁物質の排出ポイントが特定できる負荷
面源負荷 :汚濁物質の排出ポイントが特定しにくく、面的な広がりを持つ負荷
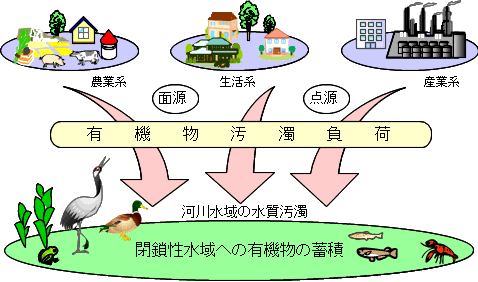 |
| 水質問題の原因 |
河川の水質問題
本来、河川は、水面を通して空気中から水中へ酸素が溶解され、植生や微生物などによる自然の浄化作用を備え、水質を改善する機能を持っていました。急流など水面の波立ちが大きい程、酸素の溶解効率が良く、平野部の流れの遅い静水面では溶解速度は落ちます。
溶存酸素DOは、20℃の清澄な水では8.84mg/lが飽和であり、このDOの豊かな水域では河床等に生息する微生物が活性化され、汚濁物として流入する有機物を分解・合成し、水質を浄化しています。
河川に流入する有機汚濁物が増加すると、微生物が有機物を分解するときに利用する酸素量が、空気中からとけこむ酸素量を上回るようになり、水中の酸素が少なくなると、好気性微生物が死滅していき、分解が進まず有機汚濁物が蓄積されて腐敗します。この結果、透明度はなくなり、悪臭を放ち、外観も水質データ上でも汚濁した状態となります。
このような河川の水質汚濁現象は様々な悪影響をもたらします。
●生活圏への影響
汚濁された河川は、透明度を失い、悪臭を放つ劣悪な環境となり、良質の空間環境的要素が失われた状態となります。都心部など人口密集地の流れの遅い平野部の河川ではこのような状況になりやすいです。
●魚類等水生生物への影響
魚類や水生生物の大半は好気性生物で水中の溶存酸素は不可欠であり、常時DO3mg/l以上は必要とされています。DO3mg/lに満たない状況は、生物の生息環境として適さないので無生物化し、水生生物はじめ魚卵などもDO不足から死滅します。
また、水生植物等も汚濁による太陽光の透過度の減少により光合成が行われず、河床での無酸素状態は根腐れなどを引き起こし、減退することになります。
生物にとってもう一つの大きなダメージは有害・有毒物質、重金属類の河川流入です。工場等の一時的な操作ミスにより、魚類が死滅するなどの例がありますが、工場等への規制や監視がないところでは有害、有毒物質が常時流下していることも考えられ、慢性的無生物状態の可能性もあります。
●水利用への影響
最も多い水利用である農業用水への影響は、有機物障害、栄養塩障害、重金属障害などがあります。有機物の多い水は、土壌の嫌気化、根腐れを生じ、窒素を多く含む水は水稲等で葉の過繁茂を生じるなど問題となります。病原性細菌や重金属の汚染を受けた河川水を農業用水として利用した場合などは、人体へ悪影響を及ぼすおそれもあります。
工業用水の利用は、冷却用水、洗浄用水などですが、最も問題になるのは、配管系統に発生するスケールによる通水能力の低下や、電気腐食による管路障害などです。したがって、スケールや、電気腐食に影響する水質項目が環境指標となっています。原料用水や精密、電子加工用品などの洗浄水の場合は、その用途によって指標が定められています。
湖沼での水質問題

湖沼は、生活用水をはじめとする貴重な水資源の安定的な供給源となり、水産資源を育み、あるいは辺の自然環境と一体となって自然探勝等野外レクリエーションの場となり、人々の生活と生産活動を支える上で重要な資産であるということができます。
しかし、湖沼水質保全特別措置法制定時(昭和59年)以前の湖沼の水質の状況をみれば、湖沼周辺で営まれる社会・経済活動の発展に伴って、流入する汚濁負荷が増大し、著しく汚濁が進行していました。
それらの湖沼においては、著しい水質汚濁のために、上水道障害、水産被害、観光的価値の低下等様々な水域利用上の障害が発生するに至っています。
水質汚濁による富栄養化現象によって様々な影響がもたらされます。
●上水(飲料水)への影響
・異臭味障害
・ろ過障害
・栄養塩の溶出及びFe、Mnの溶出
●親水活動への影響(景観障害等)
・アオコ
・淡水赤潮
●富栄養化とアオコ

富栄養化とは、リンや窒素などの栄養塩類が増大し、水生植物および藻類が増大する現象をいいます。
窒素やリンは工場排水や生活排水に含まれており、これら人間由来の窒素やリンが湖沼や内海などの閉鎖性水域に流入、蓄積することで藻類の異常増殖の原因となります。
春から夏にかけて水表面が暖められると、水表面には温度が高い層、深水部には温度が低い層が形成されます。7月〜8月ごろ表層水は最も暖められ、上下の水の自然循環が起こりにくくなります。すると、深水部には酸素が供給されなくなり溶存酸素が不足し、水質悪化の原因となります。
そのような状況で富栄養化が進むと、表層では植物プランクトンが異常繁殖して緑色や褐色の水色を呈して水面に広がる水の華といわれる現象が発生します。水の華を発生させる代表的な植物プランクトンには、渦べん毛藻類やラン藻類などがあります。なかでもラン藻類のミクロキスティスは、水面に緑色の絵の具をまいたような色となることから、アオコと呼ばれます。
アオコの発生は様々な問題を引き起こします。
・pHの上昇
・溶存酸素の低下
・魚類の大量へい死
・悪臭
・浄水過程でのろ過障害
●水生生物への影響
水生生物類は、動植物プランクトンや、底泥中に生息する底生生物、魚類やヨシなどの大形の水生動植物を含むため、水質汚濁による影響の内容と程度は多岐にわたります。
富栄養化の程度により生息する魚類が変化したり、大量発生した植物プランクトンが一時大量枯死し、酸素消費が著しくなり、無酸素水塊を形成すると生物のへい死を招くことになります。
●水産業におよぼす影響
水質汚濁による水産被害は、排出種類や被害魚介類も多岐にわたり、全国範囲で多種多様な形で発生しています。
魚類は、様々な汚濁物質の直接被害により影響を受けると同時に、水生生態系の頂点に位置し、アオコ等の藻類発生からも間接的に影響を受け、食物連鎖により長期的影響も受けます。
水産業におよぼす影響因子は、下記の通りである。
・水温の影響
・溶存酸素の欠乏(DO低下)
・塩素の影響
・富栄養化障害
・化学物質
・ダイオキシン類による汚染
海域での水質問題

●海域での水質問題の特色
二十世紀における先進国の高度成長によって引き起こされた劣悪な海洋汚染は、突発的事故を除き改善の方向に向かっています。しかし、全ての排水が、最終的に海洋に流出することから根源的には
解決されていません。また、アジアやアフリカなどの途上国において、経済発展が顕著となり、工業生 産量とともに汚染物質排出量が増大することにより、地球規模での海洋汚染は拡大しています。
沿岸地域では、都市開発や防災工事のため埋め立てや浚渫が継続的に施工され、都市部の沿岸海 域には、あっという間に人工構造物が建造されます。都市開発や埋め立てをまぬがれた内湾の漁場は、過密養殖などで環境悪化の一途で、かつての好漁場は、海藻類の枯れ死により「磯焼け」と言われる状 態となり、それによって、生息するアワビやウニ、磯付き魚などの収穫が激減しています。
一方、私たちの豊かな生活から、大量の窒素やリンが継続的に排出され、海域における生態系バランスを崩しています。富栄養化現象を引き起こし、植物プランクトンが大増殖をして「赤潮」を発生させています。さらに、海底が無酸素状態になると、酸素の含有量が極端に少ない貧酸素水塊ができ、夏季に海面上に移動し「青潮」を発生させます。富栄養化はヒトデやクラゲなどの大量発生を招き、海藻類や珊瑚などにダメージを与え、赤潮や青潮の発生により、さらに浅い海の環境は破壊され「磯焼け」が拡大します。
●海洋汚染の要因
・化学物質
内陸より、農薬、合成繊維、プラスチック、合成洗剤など、膨大な種類の化学物質が雨などによって洗い流され、最終的には海にたどり着くことになります。この影響により、化学物質は河水のほか魚介類を含むほとんどの海洋生物から見つかっています。
・重金属
海水中の有機水銀、カドミウムなどの重金属の大量摂取による公害病は日本においても深刻な問題となりました。
・内分泌撹乱化学物質
船底、養殖で使う生け簀には、貝類などの生物が大量に付着します。これを防ぐためにトリブチスズやトリフェニルスズなどのスズ化合物が使用されるため汚染されます。汚染に弱い生物種は減少し、特に海産巻貝類には、生殖器の異常などが多く出現しました。
・油汚染
油汚染の排出源は、船舶からのものが大半を占めています。油の流出は、事故によるものだけではなく、船体を海水で洗う際に捨てられる油類や、バラスト水による原因も多くを占めます。
・生物汚染
船舶の積み荷の上げ下ろしに伴って発生する船の安定性を保持するうえでのバラスト水の入れ替えは、寄港地の内湾の海水を汲み上げて自国などの内湾で排出するという操作を伴うため、有毒藻類、有害貝類などの移動が生じ大きな生物汚染が引き起こされる場合があります。このため、バラスト水対策は国際問題となってきています。引用: 「炭素繊維水利用技術設計指針 −環境水編−」 (炭素繊維水利用研究会)
●海洋汚染の現象
◇磯焼け
淡水と海水が混ざり合う汽水域が、豊かな海となるために不可欠な海藻類の繁殖は、内陸部より供給される鉄分などのミネラルが重要な働きをします。内陸部の森では落ち葉などが腐葉土となり、大地には鉄分など鉱物資源が含まれています。雨水は、森の表層を流れ、大地に浸透して河川に集約され、流れ出る水には鉄分など様々なミネラルが溶け込みます。そのミネラルを豊富に含んだ水が、河川から海洋へと流れ出て、汽水域の海藻類に吸収され、海藻類は繁殖することができます。
しかし、近年、内陸部では都市化が進み、河川源流部ではダムが建設され、下流域では護岸など河川改修が行われたことにより、大地のミネラルは海まで流れ出づらくなりました。さらに、ミネラル供給源の森林は、林業の衰退などにより、手入れが行き届かず荒廃しています。森林の育むミネラル鉄分が、海に供給されなくなり海藻類は繁殖できず、磯焼けとなっています。
◇赤潮
日本など先進国においては、下水道普及や排水処理技術の進歩により、特定発生源からの点源負荷は減少し、有機物や化学物質による水質汚染は改善に向かっています。しかし、排ガスや農業排水などからの面源負荷は減少せず、窒素やリンの排出は増加しています。一方、急速な経済発展をする後進国では、工業生産量の増大や生活環境の向上により、処理設備が間に合わず、大量の汚濁物質が未処理のまま排出されています。この窒素やリンなどの栄養塩類は、河川から海洋へと流れ込み、汽水域は富栄養化状態となり、植物プランクトンが大量発生し「赤潮」となります。
赤潮の詳細はこちら!
◇青潮
赤潮など大量発生した植物性プランクトンの死骸が海底に溜まると、その分解に大量の酸素が消費され海底は無酸素状態になります。また、沿岸の埋め立てや大型船航路造成のため海底から土砂を浚渫しますが、浚渫した後の大きな穴が放置され、穴の中の海水はほとんど移動せず無酸素状態になります。これら無酸素水には、海底の硫化水素が含まれるため、この硫化水素が海面近くの酸素と化学反応を起こすとエメラルドグリーンの「青潮」となります。
|
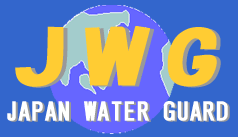 JWG ジャパン・ウォーター・ガード
JWG ジャパン・ウォーター・ガード