
§4.おいしい水

おいしい水というと、ほとんどの人は山間地の湧き水・清水を思い、名水を容器に詰めた 「 ミネラルウォーター」を思い浮かべるのではないでしょうか。 水道水もカルキ臭のするまずい水から、高度浄水処理によりおいしい水へと変わり つつありますが、ミネラルウォーターの売り上げは、水道水の約1000倍の価格にも関わらず急増しています。
店頭に並んでいるミネラルウォーターの銘柄をみると、日本の有名な産地や海外産地のもの、深層海洋水などその種類も豊富で、現在国内で市販されているものは500銘柄を越えています。その成分としてミネラル分が含まれていますが、 どのくらい含まれているのか、そのミネラル分とは何かなど、知る人は少ないのではないでしょうか。なぜミネラルウォーターを飲むのかといえば、水道水に比べ「おいしいから」「安全だから」、 反対に「水道水がまずいから」、そして「不足しているミネラル分が得られるから」と答える人がほとんどといえます。 それでは一体おいしい水の決め手は何なのでしょうか?
農林水産省「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」によると
(平成2年3月制定、平成7年2月改訂)
- 1.ナチュラルウォーター
- 特定の水源から採取された地下水を原水とし、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの
- 2.ナチュラルミネラルウォーター
- ナチュラルウォーターのうち、地層中の無機塩類(ミネラル分)が溶け込んだ地下水を原水としたもの。天然の二酸化炭素が溶けて発泡性のある地下水も含む。
- 3.ミネラルウォーター
- ナチュラルミネラルウォーターを原水として、品質を安定させる目的等のためミネラルの調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合等行われているもの
- 4.ボトルドウォーター
- 飲用水1,2,3以外のもの
今飲んでいる水はどの分類に当てはまるか確認をしてみてください。

全く何も含まれない純水がおいしいと思われがちですが、これはおいしくなく、 水の味を決めているのは、それに含まれるミネラルなどの成分です。 雨水は、地球上に降った後に、地質層や岩石層の狭い隙間に浸み込み、 いろいろなミネラル成分(カルシウム、マグネシウムなど)を溶かし込みます。水に味があるというのは、飲み水が純粋なH2Oではなく、鉱物分などを溶かし込んでいるからなのです。天然ミネラル水の中には、岩盤の鉱物、苔や藻などの微生物など実に500種以上の物質がほどよく溶け込んでいます。
さらに水には軟水と硬水という分け方があり、水に含まれているミネラル成分(カルシウム、ナトリウム、カリウムなど)によって分けられます。 1リットル中の硬度100mg以下が軟水、200mg以上が硬水とされ、中間を中硬水としています。
日本の水の場合はほとんどが100mg以下の軟水です。この硬度は水の味を決める大きな要素の一つで、一般的に硬水は口に含むと引き締まった味がして、冷蔵庫で冷やせば、味のクリスタル感は一層強調され、よりおいしく感じると言われています。一方、軟水は口の中で優しく広がります。香りや風味を大切にする日本茶や紅茶などをいれるときは、軟らかい水が向いているようです。
そこで、市販されている主なミネラルウォーターの成分を次に示します。日本人はもともとミネラル分の少ない軟水を飲んでいるため、外国産のミネラルウォーターは、硬度が高く、あまりおいしく感じない、とよく言われていましたが、フランス産の硬度が高い水でもおいしく感じるためか人気があります。したがって、水の味を決めているのは硬度だけではなさそうです。
※水の硬度=カルシウムmg/l×2.5+マグネシウムmg/l×4.1=硬度mg/l
市販されているミネラルウォーターの成分
名 称 |
ナトリウム |
カルシウム |
マグネシウム |
カリウム |
硬 度 |
産 地 |
嬬恋の天然水 |
0.39 |
0.60 |
0.06 |
0.16 |
17 |
日本 |
南アルプス天然水 |
0.65 |
0.97 |
0.15 |
0.28 |
30 |
日本 |
六甲のおいしい水 |
1.69 |
2.51 |
0.52 |
0.04 |
84 |
日本 |
龍泉洞の水 |
0.23 |
3.52 |
0.22 |
0.03 |
97 |
日本 |
エビアン |
0.5 |
7.8 |
2.4 |
0.1 |
291 |
フランス |
ヴィッテル |
0.73 |
9.11 |
1.99 |
0.49 |
307.1 |
フランス |
ペリエ |
1.15 |
14.9 |
0.7 |
0.14 |
400.5 |
フランス |
コントレックス |
0.91 |
48.6 |
8.4 |
0.32 |
1551 |
フランス |
(単位 ミネラル類:?/100ml 硬度:mg/L)
厚生労働省(旧厚生省)が1985年に行った「おいしい水研究会」の調査結果によると次のような項目があげられています。

・蒸発残留物(ミネラル):30〜200mg/l
・硬度:10〜100mg/l
・遊離炭酸:3〜30mg/l
・過マンガン酸カリウム消費量:3mg/l以下
・臭気度:3以下
・残留塩素:0.4mg/l以下
・水温:最高20度以下(10〜15度がよい)
このあげられた項目の味についての影響は、次のようです。
- ・蒸発残留物
- ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、マンガンなどのミネラル分の量です。ほどよく含まれると水の味がまろやかに、多いと水に渋みや苦みを感ずるようになります。
- ・硬度成分
- カルシウムやマグネシウム分のことでミネラルの主要成分ですが、これが不足すると水の味のまろやかさが失われます。
- ・遊離炭酸
- 水に溶けた炭酸ガスのことで、これが水に多く含まれると、炭酸飲料のように水に清涼感を与えます。多すぎると刺激になります。
- ・過マンガン酸カリウム消費量
- 水中の有機物濃度の指標になる数値です。これが多いと水にカビ臭などの異臭味や渋みを与えます。
- ・臭気強度
- 測定しようとする水を無臭の水で希釈し、無臭になったときの希釈倍数を言います。「カビ臭」は特に問題になります。
- ・残留塩素
- 消毒に使用されたのち水に残っている塩素の量です。法律で水道水には蛇口から出る水に0.1mg/l残留することが定められています。
この量が多いと「カルキ臭」となり水はまずく感じます。
- ・水温
- 水温は特に水のおいしさを左右する要因となります。10〜15℃の水は、人に最も清涼感のあるおいしさを感じさせると言われています。
最近、水のおいしさを示す指標に新しい考え方が出てきています。それは「O−インデックス」と言うものです。
これは、マグネシウム(Mg)や硫酸イオン(SO4)は少ないほど、逆にカルシウム(Ca)やカリウム(K)は多いほど水がおいしいというものです。日本の水は、8割以上が2.0以上に当てはまると言われています。
水のおいしさは、成分だけでなく、特に水温によってもおいしさが左右されます。おいしくないと悪評の高い水道水でも、残留塩素によるカルキ臭を抜いて、冷蔵庫で水温10〜15℃に冷やせば、ミネラルウォーターと味分けできないかもしくはそれ以上おいしい水になります。
東京都では高度浄水処理した水道水をボトルドウォーター「東京水」として販売もしています。
試しにミネラルウォーターと飲み比べてみましょう。
| 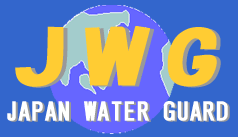 JWG ジャパン・ウォーター・ガード
JWG ジャパン・ウォーター・ガード







